概要
- ホーム
- 概要
About BEYOND 2050 “Beyond 2050”とは?
京都大学は、1200年続く京都という地において、
研究を通じ叡智を生み出してきたからこそ、
将来にわたって地球社会の調和ある共存に貢献できると考え、
成長戦略本部に「Beyond 2050」を設置しています。
「Beyond 2050」では、あらゆる分野の研究者・学生が従来の学問分野の枠組みを超えて議論し、
2050年以降も通用するアジア発の新たな価値基準に基づく未来の社会像を提示します。
ロゴについて
商願2023-132888
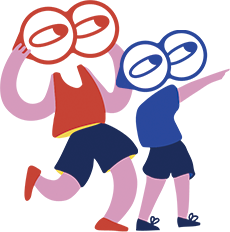
“遠い” 未来 について考える
集まってきた人々全員の、未来を見つめてそれを研究する、熱心な表情を表現したロゴです。目を細めて真剣に考える“ 難しい顔”の裏には、好奇心とワクワク感に満ち溢れた研究者の心があります。
専門が異なる人々が集まって、研究して、議論して、新たな領域・価値観を生み出して、発信する。そして、それに共感し、心惹かれた人々が集まってくる。そうした好循環が生まれるように、祭りのような楽しいイベント感のある印象的なロゴになっています。
Beyond 2050構想室メンバー
Beyond 2050構想室 室長・京都大学名誉教授石原 慶一
2050年は二酸化炭素排出を実質ゼロにするカーボンニュートラル達成の目標年です。
カーボンニュートラル達成に向けた技術開発や制度設計など様々な取り組みがなされています。
しかし、カーボンニュートラルが達成された後の社会やエネルギーシステムについてはほとんど語られていません。
我々はカーボンニュートラル社会にも様々な形があり、理想とすべき社会を定めたのち、それを実現する取り組みを行うべきだと思っています。さらに、大きな社会変革はエネルギーシステムにとどまりません。例えば、内閣府では9つのムーンショット目標を定めています。そこでは健康、災害をはじめ様々な制約から解き放たれる社会がそれぞれ想定されています。
しかし、これらの社会に共通点は見出せません。我々は、このような科学技術が実現されたのちの社会について、あらゆる学問の最新の成果を踏まえ、多方面から検討し我々の目指すべき社会を提示し、その社会の実現の妨げになるような課題を明らかにし、それを克服するための新しい取り組みを進めてまいります。
趣旨にご賛同いただけるみなさまからの物心両面のご支援(👉こちら)をお待ちしています。


